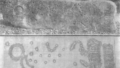千澄さんの遺作展をやりましょう。その遺作集を作りましょう。と、娘の二人の友人に言われ、そういう弔い方もあったのかと、私は喜んだ。
娘の千澄は一生病に苦しんでいたが、その病を多くの心象風景に残していた。その中で私の心に残っていた絵は、画面いっぱいにむらがっていた蛇のような生き物のうろこが漢字でぎっしりうまったものだ。でも私はその漢字がなにを語ったものかわからなかった。するとそんな私に気がついたように娘が私にいった。
「この漢字は般若心経よ」
「そうか、般若心経か」とわたしはつぶやいたが、その絵を再び見られると、この二人の言葉に喜んでいた。
この二人が私の家に来たのは、娘の死を弔うためだった。二人の友人とは小学校からの親友である深澤美保さん、もう一人は絵を通して知り合った画家の団野雅子さんである。
娘の千澄が死んだのは、全く突然のことだった。
昨年の十月のある朝、例によって娘の様子を見に行くと、娘が今日は具合が悪いといった。娘は病気だったがいつも元気だった。
私が救急車を呼ぼうかどうしようかと迷っていると、娘がさっさと自分で救急車を呼んだ。ああ、その程度かと私は安心し、娘につきそって、救急車に乗り込んだ。
病院まで五分とかからなかった。
その間、私は娘とひとことも言葉を交わさなかった。
娘が車からタンカにのせられた時、私ははじめて「ガンバレよ」と声をかけようとして、私の口は凍りついた。娘はすでに息をしてなかったのだ。私は娘との別れにあたって、とうとうひとことの励ましの言葉も言えなかった、別れの言葉も言えなかった。それが何とも言えない心残りだった。
それはともかく、二人の友人のおかげで、娘千澄の遺作展がはじまった。その最初の日私はこれから心いくまで娘の絵が見られると、娘の遺作展に行き、娘の絵に囲まれ、何とも和やかな楽しみにひたっていた。すると不意に娘の声が聞こえてきた。
「おやじ元気かい」
「ああ、元気だよ」と言いながら、ああ、そうだったのか、ここは私達最後の別れの場だったのかと、そんな場を作ってくれた娘の二人の友人に頭を下げながら、なおも娘と話しを楽しんだ。
「おやじ、この論文はなかなかおもしろいよ」
と娘が、私の「酒折宮問答歌再考」を読んでいった。
「そうか、わかってもらえたか。それはよかった」
と私は喜んだ。
「それにしても、この論文をどうやって公開するのよ」
「まだ考えてないな」
「そうか、それなら私がパソコンで打ち込んで公開しようか」
「そうしてもらえたら嬉しいな」
「私もおやじの論文に参加できて嬉しいよ」
と娘も笑いながらいった。
あの蛇のような生き物のうろこをぎっしりとうめた漢字についても父と娘の話しとして生まれ変わった。
「おまえがあんなふうに蛇みたいのもののうろこにびっしりと般若心経の文字でうめた気持ちがよくわかるよ」
「わたしは人にわかってもらうために、般若心経でうろこをうめたわけじゃないわ」
「えっ」
「そうよ。ともかくうめたのは、うめたかったからよ。わかってもらおうなんて考える余裕なんか全くなかった。」
「そうか、よくわかったよ」と言いながら、気が付くといつの間にか私は娘と一緒に、般若心経をとなえていた。
そうかこれが私達の般若心経だったのかと、私は千澄の笑顔をながめている。
「それはともかく」と私は会場を見まわしながら言った。「こんなふうに話しができるような会場を作ってもらえるような素晴らしい二人の友人をもつことができたとは、なんとも素晴らしい人生だったな。よかったな」
「うん、わたしもよかったと喜んでいるんだよ」
「さて、この会場でおまえに対する最後の言葉は、ガンバレだよ。もっとおまえの絵を見たいからな」
「うん、パパの気持ちはわかってるよガンバルよ」